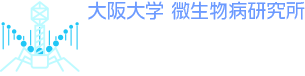常在微生物叢とヒト疾患をつなぐ鍵微生物(群)の解明
ヒト疾患においては、常在微生物叢の構成異常が病態の発症や進展に関与していることが明らかになりつつあります。特に、疾患に関連する特定の「鍵となる微生物(群)」が、病態形成において重要な役割を果たしていると考えられています。これまでに、肥満や糖尿病に関連する Thomasclavelia ramosa (旧Clostridium ramosum)(Gastroenterology, 2019)、移植片対宿主病に関連する Enterococcus faecalis(Nature, 2024)、腋臭症に関与する Staphylococcus hominis(J Invest Dermatol, 2024)など、さまざまな性質を持つ共生病原細菌(pathobionts)を報告してきました。腸内をはじめとする微生物叢は、構成する微生物間で機能を補完し合いながら、複雑な生態系を形成しています。したがって、単なる構成比の変化だけではなく、個々の微生物が有する「機能」を包括的に把握することが、微生物叢の理解と疾患との関連性を解明する鍵となります。1945年にReyniersによって開発された無菌動物飼育装置により、無菌動物(germ-free animals)の飼育と、特定の微生物のみを導入したノトバイオート動物(gnotobiotic animals)の樹立が可能となりました。私たちの研究室では、最新のメタゲノム解析技術とノトバイオート動物モデルを組み合わせることで、共生病原細菌の機能解明と、微生物叢を標的とした新たな疾患制御戦略の構築を目指します。また、微生物のシングルセル解析などの先端技術を活用し、腸内におけるアーキア(古細菌)の多様性や機能、微生物叢との相互作用についても解析を進めていきます。
ファージ由来の溶菌酵素を用いた疾患制御法の開発
疾患の発症や進行に関連する共生病原細菌を標的とした新たな治療戦略として、菌特異性の高いファージ由来の溶菌酵素を活用した手法の開発を進めています。これまでに、グラム陽性菌に対しては、細胞壁の主要構成成分であるペプチドグリカンを標的とするエンドライシン(endolysin)の有効性を実証してきました(Cell Host Microbe, 2020; J Invest Dermatol, 2024; Nature, 2024)。今後は、この知見を多剤耐性菌への応用につなげるため、機能的多様性を持つエンドライシンライブラリーの構築を計画しています。一方、グラム陰性菌は外膜に存在するリポ多糖(LPS)が溶菌酵素の作用を阻むため、従来のエンドライシンの効果が限定的でした。この課題を克服するため、LPS層を分解・透過可能な新規酵素の探索に取り組んでおり、メタゲノムデータを活用して候補酵素のスクリーニングを進めています。ファージ由来の溶菌酵素は、その高度な菌種特異性と即効性から、抗菌薬耐性の克服や感染症治療にとどまらず、特定の微生物が関与するさまざまな疾患の制御に貢献し得る新たな分子ツールとして、大きな可能性を秘めています。
ファージ療法の実用化研究
ファージ療法は、現在国内では未承認の治療法ですが、薬剤耐性菌対策の有力な選択肢として世界的に注目を集めています。私たちはこれまでに、Enterococcus faecalis を標的としたエンドライシン製剤の開発を、企業との共同研究により進めてきました。さらに、2024年4月には、国内初となるファージ療法の臨床試験(jRCTs051230164)を開始し、基礎研究から臨床応用への橋渡しを実現しつつあります。しかし、国内ではファージ製剤の製造体制や臨床試験の実施に関する知見が依然として限られており、実用化に向けた課題も多く残されています。そこで私たちは、国内外のファージ研究者や関連機関と密接に連携しながら、基礎研究・製剤開発・非臨床評価・臨床試験に至るまでを一貫して進める体制の構築を目指しています。これにより、日本におけるファージ療法の実用化と普及に貢献したいと考えています。